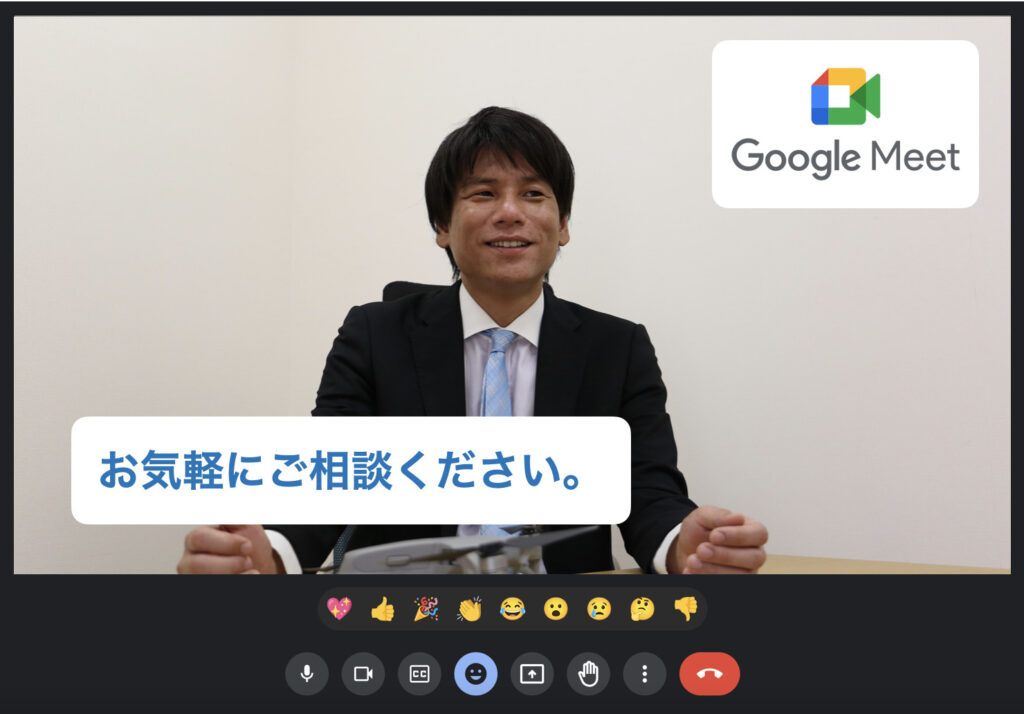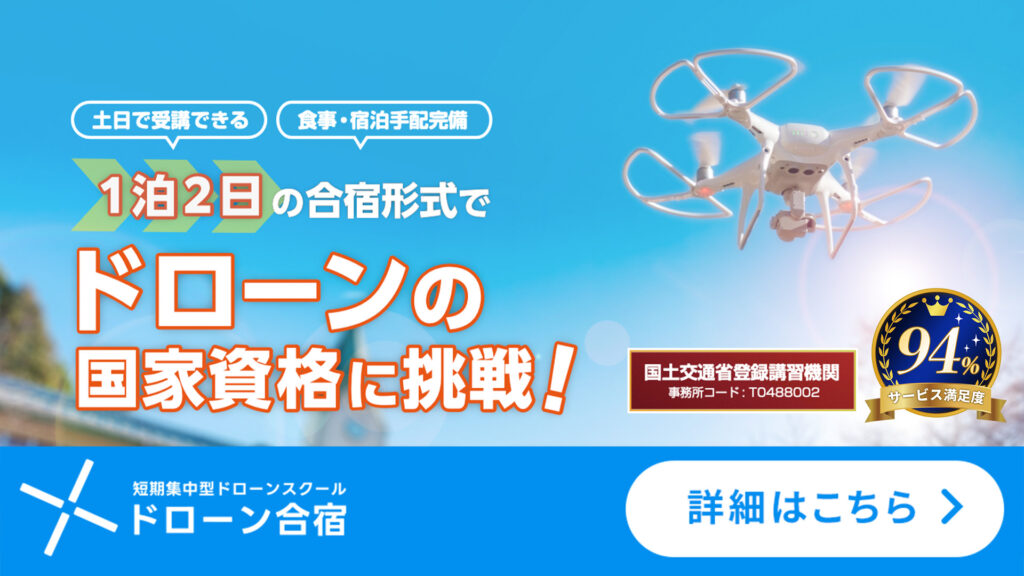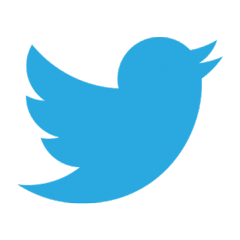災害対応で注目されるドローンの活用方法とは?活用事例や課題を徹底解説!

地震や豪雨、土砂崩れといった自然災害が発生した際、現場では一刻を争う判断と安全確保が求められます。
近年注目されているのが、空から被災状況を把握できるドローンの活用です。
上空から広域を撮影して被害状況を迅速に確認したり、赤外線カメラで生存者を探知したりと、従来の調査手段では難しかった支援が可能になっています。さ
らに、物資輸送や通信中継といった機能も備え、救助活動を大きく後押しする存在となっています。
本記事では、災害対応でのドローンの役割や具体的な活用事例、導入によるメリット・課題について解説します。
・災害対応で活用されるドローンの特徴や機能
・災害時におけるドローンの活用件数
・災害対応での具体的な活用方法5選
・災害対応におけるドローン活用の4つのメリット
・災害対応でのドローン活用に伴う5つのデメリットや課題
・実際の災害におけるドローン活用事例(能登半島地震・熱海土石流・長野豪雨)
・災害時ドローン活用のまとめ
災害対応で活用されるドローンとは?
災害発生時には、迅速かつ正確な状況把握が求められます。
ドローンは上空から被災地を広範囲に撮影し、建物の倒壊状況や孤立者の有無、避難可能なルートなどをリアルタイムで確認できるため、救助活動に大きな役割を果たします。
高解像度カメラやズーム機能を搭載したモデルであれば、細部まで鮮明に確認でき、夜間や煙が立ち込める状況では赤外線カメラを用いることで、人や熱源を見つけ出すことも可能です。
さらに、GPSを活用した自律飛行機能も災害対応では重要です。
事前に飛行経路や範囲を設定しておけば、現場で操縦者が逐一操作を行わなくても、自動で巡回飛行が可能になります。
加えて、一度経路を記録させておけば、通信が一時的に途絶しても飛行を継続できるため、安定した情報収集が実現します。
このように、災害時のドローンは「迅速な情報収集」「救助活動の効率化」「安全確保」に直結する重要なツールとして期待されています。
特徴や機能
災害対応においてドローンは、迅速かつ安全な情報収集手段として注目されています。
・被害状況の迅速な把握:広域を短時間で撮影し、被災地全体を俯瞰できる
・危険地域での調査:人が立ち入れない場所でも安全に情報収集が可能
・赤外線カメラによる捜索:夜間や瓦礫下で生存者を検知できる
・救援物資の輸送:小型の医薬品や飲料水を孤立地域に届けられる
・通信インフラの補完:通信断絶時に中継機として活用し、現場と本部をつなぐ
・三次元マッピング:撮影データを解析し、復旧計画や危険区域の特定に利用できる
上空から被災地を撮影することで、道路の寸断や建物の損壊を短時間で把握でき、広域の状況確認に役立ちます。
また、人が近づけない危険な場所でも調査可能です。赤外線カメラを搭載した機体であれば、夜間や瓦礫の下でも生存者を検知でき、救助活動を大きく支援します。さらに、小型の医薬品や飲料水を運搬することで、孤立した地域への物資供給も可能です。
通信が途絶した場合には、中継機として一時的な通信網を確保でき、救助隊と指令本部の連携を助けます。加えて、撮影データを解析して三次元マップを作成すれば、復旧計画や危険区域の把握に活かせます。
このように、ドローンは「被害状況の把握」「安全な調査」「捜索支援」「物資輸送」「通信確保」「復旧支援」といった幅広い機能を持ち、災害現場で欠かせない存在になりつつあります。
災害時の活用件数
現在、ドローンは災害や事故の現場で幅広く導入されています。
たとえば、建物や山林での火災対応、山岳や海岸部での遭難者の捜索・救助活動など、従来人の立ち入りが困難だった場所でも活用が進んでいます。
消防庁の発表によれば、2021年6月時点で災害対応におけるドローンの出動件数は累計4,000件を超えており、火災原因の調査では大きな役割を果たしています。
| 項目 | 件数 |
| 火災(建物・森林など) | 702件 |
| 火災調査(原因究明) | 1,896件 |
| 自然災害(台風・豪雨・地震) | 200件 |
| 救助・捜索(山岳遭難・水難事故) | 861件 |
| その他 | 392件 |
| 合計 | 4,051件 |
参考文献:消防本部における災害対応ドローンの更なる活用推進について(通知)
災害対応におけるドローンの活用方法5選
地震や豪雨、土砂災害といった大規模災害の発生時、ドローンは迅速な状況把握や人命救助、物資輸送など多方面で活用されています。
・支援物資の搬送
・被災状況の空撮・確認
・救助対象者の捜索
・災害マップの作成
・災害発生前のリスク監視
ここでは、災害時における代表的な5つの活用シーンをご紹介します。
1.支援物資の搬送
道路の崩落や通行止めによって孤立した地域では、緊急物資の搬送が困難になることがあります。
こうした状況において、ドローンは小型で柔軟に飛行できるため、医薬品や水、食料などの必需品を被災者のもとへ直接届ける手段として有効です。
人が現場に到達できないケースでも、自律飛行可能なドローンが命を守る物資を確実に輸送できます。
2.被災状況の空撮・確認
現場への立ち入りが困難なエリアでも、ドローンを使えば上空から現場の状況を把握できます。
特に建物の倒壊、土砂崩れ、火災などが発生したエリアでは、人が現地へ向かう前に状況を確認できることが重要です。
東京都江東区では、株式会社ミラテクドローンらと協力し、橋や道路の被害状況をドローンで調査する訓練を実施。旧中川河川敷から飛行したドローンの映像は、リアルタイムで区役所に中継され、有事の際にも迅速な対応に活かせることが確認されました。
3.救助対象者の捜索
被災地での人命救助活動において、ドローンは目視では確認できない場所の捜索に役立ちます。
赤外線カメラを搭載すれば、夜間でも被災者の体温を感知し、捜索を効率化できます。
特に山林や崖地、瓦礫の中など、人の侵入が難しい場所での捜索において、ドローンは不可欠な存在となっています。
4.災害マップの作成
空撮によって得られた高精度な画像・映像データをもとに、災害エリアのマッピングを迅速に行うことができます。
ドローンによる3次元測量を取り入れれば、被害範囲や地形変化も正確に把握可能です。
こうした「被災地マップ」は、避難経路の確認、復旧作業の計画立案、人的リソースの最適配分など、多岐にわたる支援活動の基盤となります。
5.災害発生前のリスク監視
あまり知られていませんが、ドローンは「災害が起こる前」の段階でも力を発揮します。
たとえば、大雨による土砂災害が懸念される地域では、斜面の亀裂や地盤の変化を定期的に空撮し、リスクの高まりを早期に察知できます。
また、老朽化したインフラ(橋梁・堤防など)の定期点検にも有効で、事前に危険を洗い出すことで未然に被害を防ぐ体制づくりに貢献します。
災害対応においてドローンを活用する4つのメリット
災害対応においてドローンを活用することで、ヘリコプターなどの有人航空機では実現が難しいさまざまなメリットが得られます。
1.狭いスペースでも離着陸が可能
2.初動対応がスピーディーに行える
3.救助活動における人的リスクを低減
4.コスト面での負担が軽い
ここでは、代表的な4つの利点について紹介します。
1.狭いスペースでも離着陸が可能
ヘリコプターは広大なスペースや専用のヘリポートが必要ですが、ドローンは比較的狭い場所でも問題なく離発着できます。
法律による飛行制限はあるものの、都市部や山間部といった限られた空間でも柔軟に運用できる点は、大きなアドバンテージとなります。
2.初動対応がスピーディーに行える
ドローンは起動から飛行までの時間が短いため、迅速な対応が求められる災害現場において即座に出動できます。
また、人が立ち入れないような倒壊エリアや浸水地域でも情報収集が可能で、状況の把握と復旧計画の策定を素早く進められます。
3.救助活動における人的リスクを低減
人間が入りにくい危険な場所でも、ドローンなら安全に飛行して調査や物資の輸送を実施できます。
さらに、被災地を上空から撮影することで、広範囲の被害状況を俯瞰的に確認でき、救助や避難のルート設計にも役立ちます。
これにより、救援に向かう人員の二次災害リスクを最小限に抑えることが可能です。
4.コスト面での負担が軽い
ヘリコプターの導入・運用には高額な費用がかかる一方で、ドローンは機体価格が比較的安価で、維持や整備のコストも抑えられます。
さらに、操縦者の育成にかかる費用も低めで済むため、自治体やボランティア団体でも導入しやすい点が評価されています。
結果として、災害対応の体制を低コストで整えられます。
災害対応においてドローンを活用する5つのデメリットや課題
災害現場でドローンは非常に有効なツールですが、実際の運用にあたってはいくつかの制約や課題も存在します。
1.悪天候による運用制限
2.通信環境に左右される
3.一度に運べる物資が限られている
4.長距離・長時間の飛行が難しい
5.専門スキルを持つ操縦者の育成が必要
ここでは代表的な5つの懸念点を整理し、解決に向けた動きも併せて紹介します。
1.悪天候による運用制限
ドローンは空中を飛行するため、気象条件に大きな影響を受けます。特に強風や豪雨の際には、安全上の理由から飛行が難しくなります。
しかし、過酷な環境でも飛行可能な機体も登場しています。
たとえば株式会社ミラテクドローンが開発した「SOTEN(蒼天)」は、防塵・防水性能に加え、風にも強い構造で災害時にも対応可能です。
このSOTENは、2024年1月に発生した能登半島地震でも現場で使用されました。
2.通信環境に左右される
災害時には通信インフラが破壊されている可能性があり、ドローンの遠隔操作やデータ送信が困難になります。
一般的に使われている2.4GHz帯の通信は、周辺の利用状況やエリアによって安定性が下がることがあります。
この課題を解決するため、5G通信とドローンの連携が進んでいます。
NECとNTTドコモは2022年、5Gを活用した災害対応用の映像解析システムを共同開発。また、楽天グループと楽天損保も、被災地の損害調査に5G×ドローンの技術を導入する実験を行いました。
3.一度に運べる物資が限られている
ドローンは高機動で輸送に優れていますが、一般的な機体は積載重量が5〜10kg程度にとどまります。
そのため、大量の物資を一度に運搬することは難しく、孤立した地域への物資供給では何度も往復しなければならないケースもあります。
たとえば、ある被災地ではドローンが半日かけて40回も往復し、必要な水や食料を届けた事例もあります。
近年では50kg以上、さらには200kgクラスの大型貨物を運べる機体も開発されており、実用化が進めばこうした課題の解消が期待されます。
4.長距離・長時間の飛行が難しい
一般的なドローンは小型バッテリーを搭載しているため、飛行時間が短いという制約があります。
特に広範囲に被害が及んだ災害現場では、十分な情報を取得する前にバッテリー切れになってしまう恐れがあります。
この問題への対策として、水素燃料電池を利用したドローンの開発が注目されています。ミライト・ワンと近畿電機株式会社が共同で開発した「水素燃料電池ドローン」は、従来よりもはるかに長い飛行時間を実現しており、2023年3月に行われた実証実験でもその性能が確認されました。
5.専門スキルを持つ操縦者の育成が必要
\初心者でも通いやすい!/
災害時のドローン運用は、通常の飛行よりも難易度が高く、強風や障害物のある環境で安全に操縦できるスキルが求められます。
そのため、十分な知識と実技を持つパイロットを育成することが欠かせません。
こうした背景から、ドローン合宿(https://school-drone.com/)では短期間で集中的に国家資格を取得できるカリキュラムを用意しています。
初心者から経験者まで対応しており、効率的に操縦技術や法規制の知識を習得できます。さらに、合宿形式のため短期間で資格取得を目指せる点が大きな魅力です。
・国家資格に対応した集中カリキュラムを提供
・未経験者でも安心して学べるサポート体制
・実技を重視した実践的トレーニング
・卒業後も飛行支援や相談対応などのアフターフォロー
特に一等資格を取得すれば、一定条件下で第三者上空の飛行や有人地帯での目視外飛行が可能になり、災害現場でも幅広い任務を担えるようになります。
資格取得はスキルの証明となり、信頼性向上にもつながるため、災害対応を担う人材にとって大きな強みと言えます。
災害時のドローン活用事例3選
ここでは、災害時のドローン活用事例を1つずつ紹介します。
事例①能登半島地震でのドローン運用
事例②熱海市の土石流災害
事例③長野県飯田市の豪雨災害対応
以下に、実際の災害現場でドローンがどのように活用されたかについて、3事例を紹介します。
事例①能登半島地震でのドローン運用
静岡県熱海市伊豆山で起きた土石流災害では、ドローンによる上空からの撮影データを、災害前の地形と重ね合わせた立体的な「状況図」が制作されました。
この3Dデータにより、土石流の流れや家屋被害を的確に把握でき、関係機関間での円滑な情報共有と二次災害の予防に大きく貢献しました。
事例②熱海市の土石流災害
2024年1月に発生した能登半島地震では、輪島市からの要請を受けた5社のドローン関連業者が出動。被災地の捜索、状況把握、支援物資の輸送など多角的にドローンを活用しました。
特に、狭小空間に入り込める専用ドローンによる倒壊建物内の安全確認や、処方薬・生活必需品・軽食などの物資配送が実施されました。
また、空撮によって地すべりの兆候や地割れの全貌把握にもつながりました。
事例③長野県飯田市の豪雨災害対応
令和5年6月の豪雨により発生した長野県飯田市の道路崩落や橋流出では、ドローンによる空撮が直ちに実施されました。
撮影した資料は迅速な災害査定に使用され、迅速な復旧判断と支援体制の構築につながりました。
まとめ
ドローンは災害現場において「被害の早期把握」「人命救助の支援」「通信や物資輸送の補完」など、多岐にわたる役割を担っています。
狭い場所でも離発着でき、初動対応を素早く行える点は大きな強みです。
一方で、悪天候や通信環境の制約、積載量や飛行時間の限界といった課題も残されています。
しかし、防水・耐風性能を持つ新機体や水素燃料電池ドローンの開発などにより、その弱点も着実に克服されつつあります。
今後さらに技術が進化すれば、ドローンは災害対応の現場で欠かせない存在として、より大きな役割を果たすことが期待されます。