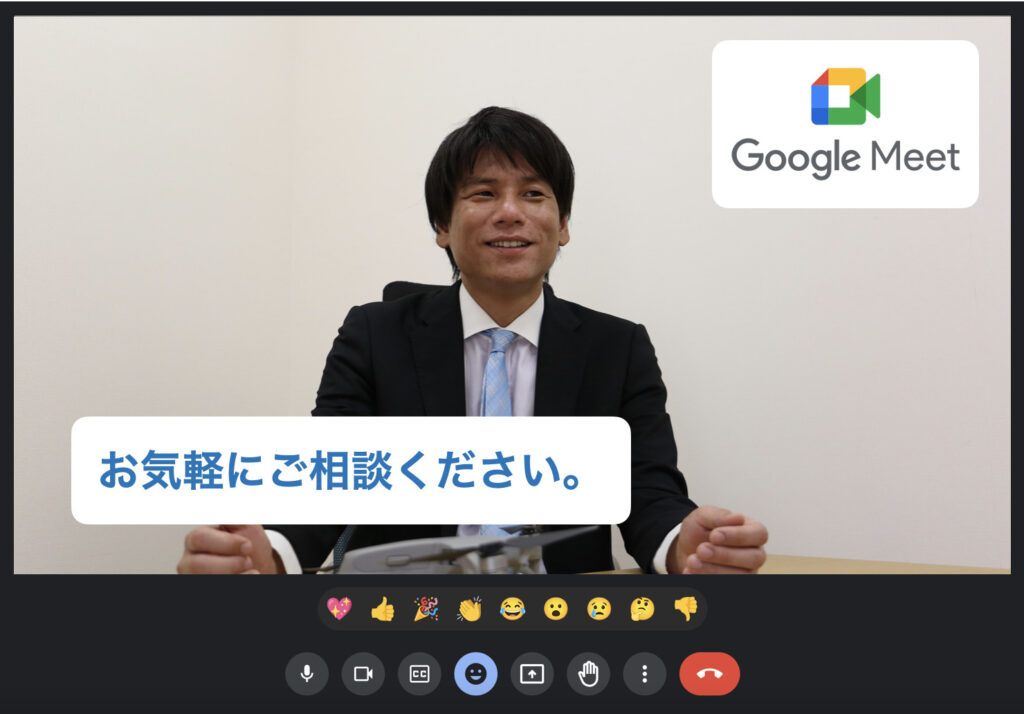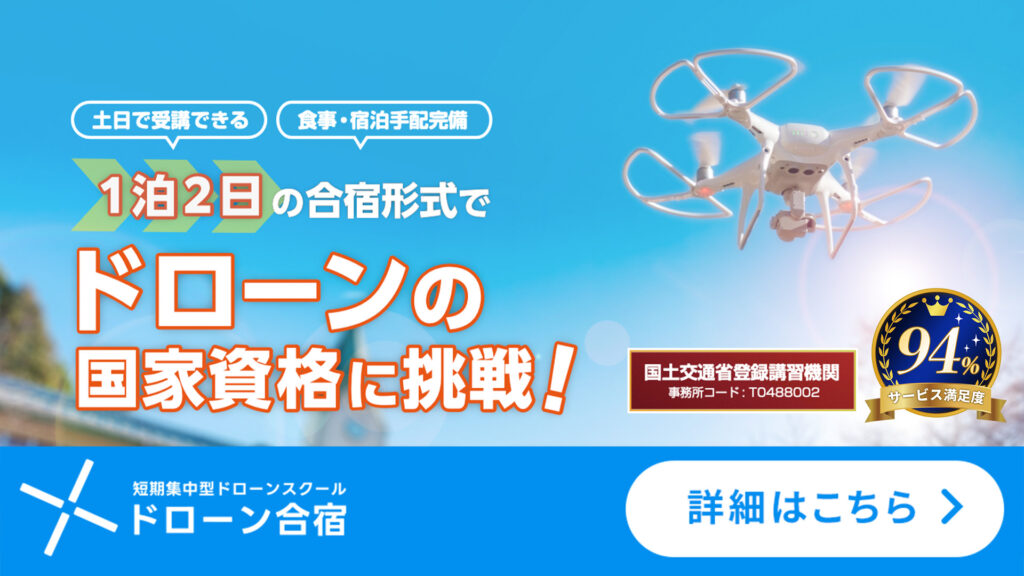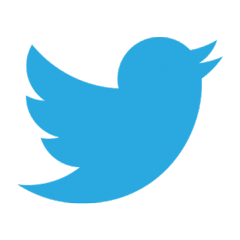ドローン免許の難易度とは?国家資格の取得方法・費用・合格率を徹底解説
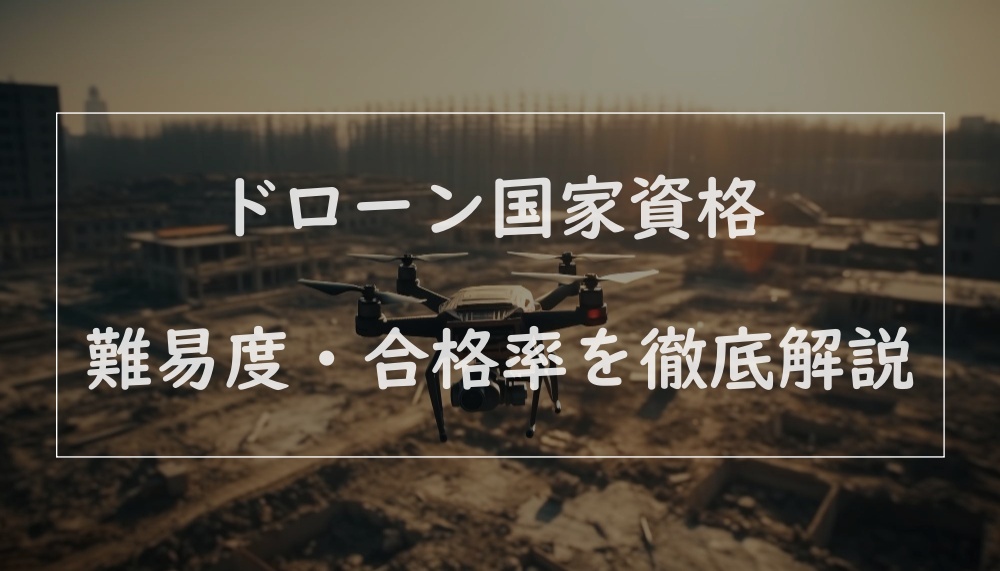
ドローン関連の資格は現在40種類以上あるとされており、「どの免許を取るべきなのか迷ってしまう」という方も多いのではないでしょうか。
実際、ドローンに関する免許や資格は、使用目的や飛行スタイル、将来的な活用方法によって最適な選び方が大きく異なります。
また、取得までにかかる日数や費用、そして何より「どれくらい難しいのか?」という点も、事前に知っておきたい重要なポイントです。
そこでこの記事では、ドローン免許の種類や難易度、国家資格の合格率、費用の目安、さらには最短1泊2日で資格取得ができるおすすめスクールまで、徹底的に解説します。
・ドローン免許(国家資格)の概要
・ドローン国家資格取得の手順
・ドローン国家資格の費用
・ドローン国家資格のメリット
・ドローン国家資格の難易度と合格率
・ドローン国家資格が取得しやすい『ドローン合宿』を紹介!
ドローン免許(国家資格)とは?
ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)は、特定の飛行方法や空域において飛行を行う際に必要とされる知識や技能を、試験を通じて確認・証明する制度です。
この制度は、航空法に基づく飛行ルールを安全に遵守するために設けられました。
資格の種類は『一等無人航空機操縦士』『二等無人航空機操縦士』の2つに分かれており、用途や飛行エリアに応じて選択されます。
一等無人航空機操縦士は、いわゆる「レベル4飛行」と呼ばれる、有人地域で第三者の上空を飛ばすような高度な運用が可能です。
一方、二等無人航空機操縦士は、人が立ち入らない区域に限定される「レベル3」までの飛行(目視外を含む)に対応しています。
つまり、一等資格は二等資格の内容に加え、よりリスクの高い飛行環境に対応するための追加カリキュラムが課される形になっています。
また、この資格には「基本」と「限定変更」という考え方が存在します。
基本は日中かつ目視内での飛行を対象とし、限定変更とは、特定の条件下での飛行(例:夜間、目視外、大型機体)を可能にするための追加項目です。
これらは追加の講習と試験に合格することで飛行許可が得られます。
資格取得にかかる費用について、試験の手数料は一定ですが、講習費用はスクールごとに異なっており、価格帯は自動車教習所のようにバラつきがあります。
なお、実技試験は機体のタイプに応じて3つに分類されます。
マルチローター型、ヘリコプター型、そして固定翼機(飛行機型)で、それぞれの機種に合わせた操縦技能が求められます。
よくある誤解として、資格を持っていないとドローンを飛ばせないと思われがちですが、実際には航空法の適用外の空域や方法であれば、許可や資格がなくても飛行は可能です。
ただし、法律に基づくルールに従って飛行を行う場合、場所や飛行方法が制限されることが多くなります。
そのため、より広い範囲で飛行活動を行いたい場合には、国家資格を取得しておくことで、許可の取得がスムーズになるというメリットがあります。
ドローン国家資格取得の手順
ドローンの国家資格を取得する方法は、大きく分けて2通りのルートがあります。
一つは「登録講習機関に通う方法」、もう一つは「講習機関を利用せずに直接受験する方法」です。
選択するルートによって必要な手順や受験内容が異なり、それぞれにメリットと注意点があります。
どちらの方法でも、学科試験の合格と身体検査の通過は共通の必須要件です。
登録講習機関を利用する場合の手順
登録講習機関に通う場合、定められた講習を修了することで、実技試験(実地試験)が免除されます。
すでに民間のドローン資格を持っている方には、条件を満たせば一部の講習が省略されることもあります。
以下のような流れで資格取得が進みます:
| 登録講習機関を利用する場合の手順 | |
|---|---|
| ① | 国土交通省で技能証明申請者番号を取得 |
| ② | 登録講習機関で講習を受講 |
| ③ | 指定試験機関で学科試験を受験 |
| ④ | 指定試験機関で身体検査を受検 |
| ⑤ | 試験に合格すれば国土交通省より合格証明書を取得 |
| ⑥ | 国土交通省から技能証明書を交付 |
登録講習機関を利用しない場合の手順
講習機関を利用せずに国家資格を取得する場合は、学科試験に合格した後で実地試験の受験が必須となります。
講習の代わりに、自身でしっかりと学習・準備する必要があります。
手順は次の通りです:
| 登録講習機関を利用しない場合の手順 | |
|---|---|
| ① | 国土交通省で技能証明申請者番号を取得 |
| ② | 指定試験機関で学科試験を受験 |
| ③ | 指定試験機関で実地試験を受験 |
| ④ | 指定試験機関で身体検査を受検 |
| ⑤ | 試験に合格すれば国土交通省より合格証明書を取得 |
| ⑥ | 国土交通省から技能証明書を交付 |
ドローン国家資格取得にかかる費用
ドローンの国家資格を取得する際にかかる費用は、スクールに通うかどうかによって大きく異なります。
たとえば「一等無人航空機操縦士」の資格取得にはおよそ70万円から115万円程度、「二等無人航空機操縦士」の場合は30万円から50万円前後が一般的な目安となります。
この費用には、講習の受講料、試験の申請手数料、免許交付時の費用などが含まれます。
さらに、「夜間の飛行」「目視外での操縦」「最大離陸重量が25kgを超える機体の操作」といった限定変更を希望する場合には、別途手続きと追加費用が発生する点にも注意が必要です。
ドローン免許(国家資格)に掛かる費用をもっと詳しく知りたい方は、以下記事を合わせてご確認ください。
ドローン国家資格取得のメリット
ドローンを操縦するために、必ずしも国家資格が必要というわけではありません。
法律で定められたルールを順守すれば、資格を持っていなくても飛行させることは可能です。
ただし、資格がない場合は、飛行できるエリアや時間帯、機体の種類などにさまざまな制限がかかり、利便性に欠ける場面が多いでしょう。
ドローンに関する資格には、国が認定する国家資格と、各団体が発行する民間資格があります。
民間のライセンスを取得していれば、国家資格(二等)で認められている「飛行レベル1~3」の範囲での操縦が可能です。
それではここから、ドローン免許(国家資格)を取得するメリットを詳しく紹介します。
1.スキルの証明
ドローンに関する技術力の証明方法には、国家資格だけでなく民間資格も存在します。
ただし、どちらがより信頼されるかという点では、国家資格の方が圧倒的に有利です。
国が認定している資格は、第三者に対してスキルを客観的に示す手段として強い説得力を持ちます。
一方で、民間団体が発行している資格は、その内容やレベルが分かりにくいため、特にドローンに詳しくない人にとっては評価しづらい場合があります。
例えば、自己紹介の場で「民間のドローン資格を持っています」と伝えても、その価値が伝わりにくいこともあるでしょう。
その点、「国家資格を保有しています」と言えば、たとえ相手が業界に詳しくなくても、「一定の技術がある人だ」と理解されやすくなります。
2.飛行申請手続きの簡略化
一等・二等の国家資格を取得することで、特定の飛行に関する申請手続きが不要または簡略化されるケースがあります。
結果として、事前の準備がスムーズになり、業務の効率化が期待できます。
申請の要否については、下記の一覧表をご参照ください。
| 飛行レベル | 国家資格:一等 | 国家資格:二等 | 民間資格 |
| レベル4 (市街地での目視外飛行) |
必須 | 利用不可 | 利用不可 |
| レベル3 (人がいない地域での目視外飛行) |
必須 | 必須 | 必須 |
| レベル2 (視界内での自動飛行) |
不要 | 不要 | 必須 |
| レベル1 (視界内での手動操縦) |
不要 | 不要 | 必須 |
3.レベル4飛行が可能になる
レベル4飛行(有人地域における目視外での飛行)を実施できるのは、「一等無人航空機操縦士」の資格を取得している人だけに限られています。
この一等資格を所持していることで、高度な操縦スキルを持つ証明となり、他の操縦士との差別化にもつながります。
ただし、資格があるからといって自由にドローンを飛ばせるわけではありません。
飛行には事前の許可申請が必要であり、申請手続きを怠ると法令違反となるため、必ず事前に対応しましょう。
ドローン国家資格の難易度と合格率
無人航空機操縦士試験の学科に関しては、合格率が公式に発表されていないため正確な数字は不明ですが、一等・二等いずれの資格試験も、おおよそ60%前後の合格率であると見られています。
二等の実地試験に関しては、55%から70%程度の合格率とされており、ある程度のばらつきがあるようです。
なお、二等資格は一等に比べて取得のハードルが低く、未経験からでも必要な知識や技能をきちんと習得すれば、十分に合格を目指すことが可能です。
ただし、これはあくまで国家資格の場合であり、自己流の曖昧な学習では合格が難しくなるケースもあるため、注意が必要です。
一方で、一等資格はより高度な知識と技術が求められる専門性の高い資格であり、プロフェッショナル向けです。
現役の操縦者であっても「難関」と口にすることがあるほどで、難易度の高さがうかがえます。
その分、取得すれば高度な操縦スキルを証明できる大きな強みになるでしょう。
どちらの資格も、独学に不安がある場合は、登録講習機関が提供する講座を活用し、専門講師から体系的に学ぶ方法が非常に効果的です。
ドローン免許(国家資格)を取得するなら1泊2日で通える『ドローン合宿』が最もおすすめ!
・国土交通省「登録講習機関」に認定されているスクール
・最短1泊2日で国家資格が取得できる
・プロのドローンパイロットからの直接指導
・受講生アンケートで満足度90%超え
・充実した屋内、屋外飛行場
・無料説明会を実施
・高知、山梨、岡山に系列のスクールがある
ドローンの国家資格は、独学でも習得可能ですが、全国各地にあるドローンスクールを受講してプロのパイロットから法規制などの知識や正確な操縦技能を学習しながらドローン国家資格を取得するのがおすすめです。
全国500ヵ所以上あるドローンスクールの中でも、最短1泊2日でドローン国家資格が取得でき、受講者アンケートで満足度90%を超える『ドローン合宿』を紹介します。
ドローン合宿は、東京都墨田区両国の株式会社メルタが運営する国土交通省の「登録講習機関」に認定されたドローンスクールです。
| スクール名 | ドローン合宿 |
| 運営会社/団体 | 株式会社メルタ(登録講習機関 事務所コード:T048001) |
| 所在地 | 〒789-0303 高知県長岡郡大豊町川口665 |
| お問い合わせ | 03-5839-2567 drone@melta.co.jp https://school-drone.com/kochi/#contact |
| ウェブサイト | https://school-drone.com/kochi/ |
| SNS | https://x.com/drone_melta |
当スクールでは、ドローン国家資格が取得できるコースとJUIDA資格のコースを用意しており、未経験者でも最短1泊2日で資格を取得可能です。
また、「楽しく・わかりやすく」を重視した短期集中合宿型で、自然豊かな環境で学べることから、県内外問わず多くの方が受講しています。
さらに、2022年3月から2023年7月までの受講生アンケートで、講習内容の満足度92%、スタッフ対応の満足度97%、アフターサポートの満足度93%を獲得しています。
ドローン合宿は、『高知校』『岡山校』『山梨校』にもスクールがあるので、お近くの方は是非受講または無料説明会に参加してほしいと思います。
ドローン合宿 山梨校
ドローン合宿 山梨校では、二等資格(二等無人航空機操縦士)が取得できる『二等 国家資格コース(初学者向け)』が受講できます。
こちらのコースは、2024年6月頃に開始いたしました。
| コース名 | 二等 国家資格コース(初学者向け) |
| 受講期間(学科) | 10時間 |
| 受講期間(実技) | 10時間 |
| 受講料金(税込み) | 242,000円 ※ホテル宿泊(1泊分)、食事(4食)、駅からの送迎費用込み |
| 取得できる資格 | 二等無人航空機操縦士 |
| 備考 | ・国土交通省発行の「二等無人航空機操縦士」の実技試験が免除となる「無人航空機講習修了証明書」を取得できます。 ・座学はオンラインで事前に学習、講習当日はしっかりと実技を学べる ・ホテル宿泊(1泊分)、食事(4食)、駅からの送迎付き ・経験者 日帰りコースは、当スクールの卒業生のみを対象とさせていただきます。 |
限定変更:夜間・目視外
ドローン合宿 山梨校では、『限定変更:夜間・目視外』が受講できます。
| コース名 | 限定変更:夜間・目視外 |
| 受講期間 | 半日ずつのカリキュラム(午前:昼間、午後:目視内) |
| 受講料金(税込み) | 33,000円 |
| 取得できる資格 | – |
| 備考 | ・1日で2つの限定解除を同時に受講することも可能です。 ・半日講習のため、ご飯と宿泊はつきません。また、スケジュールの都合上、送迎対応が出来かねます。 ・限定解除の受講を悩まれている方は、受講後に別途申し込みしていただくことも可能です。 ・国家資格コースの修了審査合格者のみ受講可能です。 ・不合格の場合、再審査(16,500円税込)を別日で受けることが出来ます。 |
ドローン合宿 高知校
ドローン合宿 高知校では、二等資格(二等無人航空機操縦士)が取得できる『初学者 二等国家資格コース』が受講できます。
| コース名 | 初学者 二等国家資格コース |
| 受講期間(学科) | 事前オンライン座学10時間分 |
| 受講期間(実技) | 実地講習1泊2日 |
| 受講料金(税込み) | 275,000円 ※ホテル宿泊(1泊分)、食事(4食)、駅からの送迎費用込み |
| 取得できる資格 | 二等無人航空機操縦士 |
| 備考 | ・国土交通省発行の「二等無人航空機操縦士」の実技試験が免除となる「無人航空機講習修了証明書」を取得できます。 ・座学はオンラインで事前に学習、講習当日はしっかりと実技を学べる ・ホテル宿泊(1泊分)、食事(4食)、駅からの送迎付き ・経験者 日帰りコースは、当スクールの卒業生のみを対象とさせていただきます。 |
ドローン合宿 岡山校
ドローン合宿 岡山校では、二等資格(二等無人航空機操縦士)が取得できる『初学者 二等国家資格コース』が受講できます。
| コース名 | 初学者 二等国家資格コース |
| 受講期間(学科) | 事前オンライン座学10時間分 |
| 受講期間(実技) | 実地講習1泊2日 |
| 受講料金(税込み) | 275,000円 ※ホテル宿泊(1泊分)、食事(4食)、駅からの送迎費用込み |
| 取得できる資格 | 二等無人航空機操縦士 |
| 備考 | ・国土交通省発行の「二等無人航空機操縦士」の実技試験が免除となる「無人航空機講習修了証明書」を取得できます。 ・座学はオンラインで事前に学習、講習当日はしっかりと実技を学べる ・ホテル宿泊(1泊分)、食事(4食)、駅からの送迎付き ・経験者 日帰りコースは、当スクールの卒業生のみを対象とさせていただきます。 |
まとめ|ドローン国家資格取得なら登録講習機関に認定されているスクールがおすすめ
ここまで、ドローンの国家資格制度、難易度の目安、取得方法、そして最短で学べるおすすめスクール『ドローン合宿』についてご紹介してきました。
以下ドローン国家資格の難易度についてまとめます。
- ドローン国家資格は「一等」と「二等」に分かれており、それぞれ対応できる飛行範囲が異なる
- 合格率は明確に公表されていないが、学科試験は60%前後、二等の実技は55~70%程度と推測されている
- 二等資格は未経験者でも合格を目指しやすい難易度。一等は実務経験者でも難しいとされるハイレベルな内容
- 国家資格取得には「登録講習機関の講座受講」または「独学からの直接受験」という2つの方法がある
- 独学は可能だが、効率よく学ぶなら講習機関の利用が断然おすすめ
- 特に『ドローン合宿』は、最短1泊2日で国家資格が取得できる短期集中型の人気スクール
- ドローン合宿は高知・山梨・岡山に展開されており、講習の満足度やサポート体制も高評価
ドローンの免許取得を目指すうえで、難易度や費用の見通しを事前に把握しておくことは非常に重要です。
特に、2025年12月からは民間資格での申請優遇が廃止されるため、将来的に業務や空撮で活用したい方は、国家資格の取得を今のうちに検討しておくことをおすすめします。